 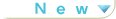
|
■ 「伝えたいこと」
|
濱崎洋三著作集「伝えたいこと」 定有堂書店刊(1998)
ISBN 9784812306109
第4部「講演」から
1996.8.18. 鳥取西高一年八組教室にて「最後の授業」 |
メールでご注文できます。 teiyu★nifty.com
★をアットマークに変えてお送りください |
|
|
| (一) 鳥取西高のこと |
座ったままで失礼します。
|
私は現在病気療養中で、日赤病院に世話になっております。ここにおられる内科の徳永先生は、私の直接の主治医ではないのですが、術後のフオローということで、世話になっています。
実は自分でもそうだなと思っているのですが、何となくここ一ケ月ほど老人性鬱病というのか、気力がない、勤めにも出たくない、本も読みたくない、電話にも出たくない、というナィナィづくしの日々が続いています。おそらくそういう私の容態に何となく勘づかれた名医の徳永先生が、「こいつ、どこか世の中に引っぱり出してやつた方が生きようという気力を持つのではないか」と考えられ、そのはからいで今日のような場が持たれたのではないかと考えています。
|
幸いなことに鳥取西高で長い間勤務させてもらいましたし、おまけに在籍中ずっと、新聞部という部の顧問を務めさせていただくという幸運な仕事もさせていただきました。
|
そのようなこともあって新聞部の部員の方々、新聞部OBの方々を中心にして、今日の会の運びになったのではないかと思います。
|
ところがこのことを考えてみますと、摩訶不思議なことがございます。それは私自身がなぜ高等学校の教員となり、なぜとりわけ西高の、とりわけ硬派の、固いといいますか、変竹林というか、高等学校の生徒にしては少し理屈つぼい生徒の多いこの学校で、理屈っぽい記事の多い新聞をつくることになったのかということでございます。
|
その原因は直接私にあるのではなく、実は私が高等学校の教員になりましたこと、また私自身が鳥取西高の新聞部の顧問になりましをことのきっかけなのですが、そのきっかけとなったのは、お亡くなりなりました香川正晴先生―鳥取西高の山のすぐそばの裏に今も香川先生の奥さまが住んでおられますが―との出会いが一番の原因であったと思います。香川先生は、当時の私にとつてのいわば「鳥取西高の自己証明」であつたと思います。この先生がいらっしゃればこそ、鳥取西高というもののアイデンテイフイケーシヨン―烏取西高そのものというもの―が得られるのだということを感じておりました。
|
先生は東京大学の文学部印度哲学科を首席でご卒業になっておられます。ただしよくお聞きしますと、そのとき東京大学文学部で印度哲学を専攻されたのは先生おひとりで、十七年ぶりのことであったそうです。必然的に卒業は首席にならざるを得ないということでした。戦後の混乱、激動時期を、先生は思想的に煩悶されながら、この鳥取西高で教鞭をとっておられました。そして西高の新聞部をおつくりなられました。
|
その先生が、私の担任となられました。それ以前の私はゴリゴリの理科系の生徒で数学ばかり勉強し、将来は医者になるのだと決めていました。その私が高校二年の時、香川先生と出会い、その出会いを通じて「人問の生き方」というものを教えていただき、「将来医者になるのだ」という方針を転換し、「自分は故郷の高等学校の教員になろう」と決め、できれば「歴史」という学問に取り組んでみたいと思うようになりました。そしてそこで自分の一生が決まったのだと思います。
|
従いまして今日この日があるのは、まず自分の一生涯の仕事があること、自分のこれまでの生活の中での楽しみであった本を読むということ、さらに若い人たちとワイワイいいながら共に遊ぶという、これらの楽しみは、香川先生から皆教わったことであります。
|
|
(二) 死期を迎えて
|
|
また私自身が死期を迎えていますが、本日の会は「最後の授業」という少し酒落たタイトルです。が、私にすれば本当にそうかなという気がしなくもない。むしろそうでない方がいい。
|
ここにおられる徳永先生に「徳永先生、笑顔で『最後』といっていいか、本当にそうか」と聞きたくなるのですが…。笑顔で「最後」といえるのは、嘘だと思うのです。笑顔でいられるのは次の機会があるからこそ、笑顔でいられるのではないでしょうか。ただ、私自身の気持ちの中には半分くらい本当に「最後」かもしれないという気があります…。
|
「最後」と言えば、私目身が病床にあった香川先生をお見舞いしたのは、先生が亡くなられる半年前でした。とても悲しいお別れをしたことを思い出します。
|
先生はほとんど冷たくなった手で私の両手を握られ、「いいか、洋三。人に向かって『糞ったれっ!』というが、これは嬉しいことだぞ。糞をたれることができる平常な人間であるということはどんなに幸せなことか。人は力を持った人問として振る舞うのが幸せなのではなく、糞がたれれるという平常な体をもった人間であるということが幸せなのだ。この普通の感覚である糞がたれれるという自分に与えられた健康を周りの多くの人に向けて感謝の念を込めながら生活すべきではないか」と言われたことを思いだします。そして、先生は「おまえと私とが最後まで違うのは、思想のあり方、生き方の拠り所の違いだ。おまえはアジアの思想、アジア的なものの考え方の中に自分の生き様を求めようとしているが、私はキリスト教というヨーロッパの考え方の中にそれを求めた」と言われました。
|
戦争中東京大学で印度哲学を専攻されていますが、戦争中にクリスチャンになられています。いわば戦前戦後の思想的混乱と自身の戦争体験の中で煩悶されながら、思想的「転向」(印度というアジア的なものからキリスト教というヨーロッパ的な患想への転換)をされています。おそらく先生は、自分の中の思想的転換である「転向」という事実を鋭く見つめられながら、西欧思想の中に人類の未来と希望を見いだされたのだと思います。
|
翻って私自身はといえぱ無宗教、無信仰です。宗教には大変興味がありますが無宗教です。ただ、思想としてはヨーロツパの思想より圧倒的にアジァの多くの思想に傾斜し、惹かれています。香川先生は、私のそのような思想的傾向をみてとられており、そのように言われたのだと思います。そして「思想的には違いがあるが、楽しい出会いであったな」と言われました。それは、九月中旬の晩秋の日でしたが、冷たくなったその手で、私の両手を握られて、そう言われたことを今でも昨日のようにありありと思い出します。
|
その香川先生へのご恩に報いる気持ちで新聞部の顧問を引き受けたのです。私は顧問となって、新聞部の生徒を「いじめ」ましたし、「からかい」ました。
|
もっとも私は新聞部部員に限らず、鳥取西高の生徒をよく「いじめ」、「からかい」ました。新聞部の生徒はまだしも、「新聞部部員以外の西高の生徒はゴミだ。自分の考え、思想を持っていない」と思っていましたからなおさらです。西高新聞部の部員と対等に話ができる西高生徒はそうそういませんでした。また新聞を読んできちんと理解できる生徒もそうはいません。
|
こんな出来の悪い鳥取西高の生徒がいる中の新聞部ですから、新聞部員といえども、そうそうまともにはつき合つてはいられません。相撲と一緒です。はじめに強い突き押しを一発かまします。そこでへこたれるようではおぼつきません。その私の「いじめ」をはね返してきて、食いついてきた生徒が、はじめて本物だ、ということになるのです。
|
|
(三)本の読み競い合い
|
|
こうした私の「いじめ」をはねかえしてきた生徒は本物ですから、できるだけの書物を貸し与え、紹介したりしました。その時私が留意したのは、いわゆる「教養書」の類は紹介しない、ということでした。私より一世代前の戦中派である昭和一桁生まれ、あるいは大正末生まれの方々が薦められた本の多くは、「大正教養本」といわれるもので、大正教養主義が思想的背景となっているものでした。
|
しかし私は一世代前の戦中派の方々のように、「大正教養本」を生徒達に薦める気にはなりませんでした。当時昭和四十年前後ですが、この頃になると、かなり大量に質の高い本が出版されていましたし、素晴らしい作者も出て来はじめていました。そしてそれらの、自分が生きている「今という時代」の事を扱つた本を大人と同じように読ませたいと思っていたからです。
|
当時大学出たての高等学校の教師である私は、生徒と年齢的に五〜十歳くらいしか違いがなく、私自身まだまだ大人とはいえない頃です。
|
一般的に、高校生にとって話が通じる教師の年齢は大体、生徒との年齢差が五〜十歳くらいか.ら、せいぜい二十四〜二十五歳くらいまででしよう。これ以上の差のあるいわば「担任のない教師」―今日の私のように、自分が高校生のときの担任の先生が既に物故されている教師―と会話を交わしても面白くはありません。
|
そこで、話の通じる、面白い会話の成り立つ同級生同士あるいは生徒と先生との間で、興味を持って対話できる本ということになると、今という時代を扱った新しい本ということになり、こういう本を読み競えば面白いと思ったのです。
|
この本の読み競い合いはいまでも続いています。先日(平成八年三月)、私は転移性の癌のため肝臓の手術を受けました。この手術のため一ケ月半ばかり日赤病院に入院しているとき、枕元に最近出版されたばかりの『宗教の時代を生きるために』(森岡正博著)という本を置いて読んでいました。そこへ、ここにおられる徳永医師がこられ「おお、先生、このような本を読まれているのですか」と聞かれるので、「二章まで読んだ。なかなかいい。これを読まないと明日を生きてはいけないという感じがする本だ。徳永先生にも是非読んでもらいたい」と薦めたところ、「私もすでに手にいれて読んでいる」とのことでした。
|
一冊の本をめぐる、こういうやりとりを周囲の人が見れば、「日赤に徳永医師あり。そして、そこに病人として入院した濱崎あり。かつての先生と生徒が、今は医者・患者と立場を換え、両者が同じ土俵の上で一冊の本を媒介として、いい勝負が始まっている」と思われるのではないでしょうか。入院中のことですが、そのようなことがあったことを思い出します。以上が、私が今日ここで講演することになった経緯です。
|
|
(四)大人を信じるな
|
|
さて、体力が衰えて、少々血の気が少なくなりつつあるので、これからお話する内容はかなりの部分を端折ることになりますが、お許しください。
|
今日ここにお集まりの方々は、一九七〇年頃に西高をご卒業になられた方々が中心ということだそうです。そこで、かつて一九七〇年頃に、私がイヤイヤながら、地元紙に初めて書いた一文を持ってきました。それをもとにお話しします。
|
当時私は、地元紙にものを書くまいと決めていました。地元紙にものを書くということは私にとってはタブーでした。そして、地元紙に一切書かないことを衿持とし、モットーとしていました。
|
しかし、私は、このタブーを破るような形で、一九七四年八月十五日に「私にとっての戦後」(『山陰中央新報』)というタイトルで地元紙に初めてものを書きました。
|
この一文で私が伝えたかったことは何か?というと、それは「大人を滅多やたらに信じてはいけない、まして大人の中でも教員というものを信じてはいけない」ということです。
|
昭和二十年八月、私は国民学校三年という時に戦争の終わりを迎えました。その戦争の終わりという貴重な体験、この時の自分の貴重な経験の一駒を、次ぎの世代の人々に何をもって語り継いでいくべきなのか、ということを考えていました。その考えの中心にあったのは先ほどの「大人を滅多やたらに信じてはいけない、まして大人の中でも教員というものを信じてはいけない」ということです。これをまず強く言いたかったのです。
|
なぜかと、言うと、子供を大人中心の都合のよい考え方-たとえば戦前の軍国思想の中に取り込むのは、大人であり、子供を取り込む罠、仕掛けとしての教育というものだからです。そして私たちは、そういう教育の罠を見抜く目をきちんと持たなくてはならない、と思っていたからです。
|
|
(五)独りで変革はできない
|
|
ただ、ここで注意していただきたいのは、大人、教育というものを全否定しているのではないことです。これらを全部否定して人間が生きていける訳は有りません。なぜなら人間は社会的動物として生きていかねばならないからです。
|
もちろん子供は、大人によって養われ、育てられて、大人が作り上げた社会の中に身を置いて成長していかざるを得ません。ではこのような状況の中で、子供は何ができるのかと言えば、それは「おかしいな」と疑ってみることではないでしょうか。
|
子供は成長する過程で、自分が生きている時代、自分の属する世代の中で感じた「おかしいな」という勘を媒介にして、少しずつ少しずつ自らを変えながら大人の世界に踏み込み、大人になっていきます。そして一方でその社会の中の「おかしいな」と思うことを、少しずつ変えていきます。それが「生きていくさま」というものなのでしよう。このように人は少しずつ自己変革を遂げながら、一方で少しずつ社会変革を行うのですが、ここで重要なことは何かといえば、決して独りで変革はできるものでなく、必ずそれは複数でなければできないということではないでしょうか。
|
人間は成長の過程で、まず自分を理解してくれる者が最低限一人必要になり、その一人をつくらなくてはなりません。いわゆる一対一の関係=ペアの関係ー吉本隆明ならこの関係を「対幻想」というでしょうがーというものを、人間はどうしても必要とし、男性は女性を、また女性は男性を「対幻想」として持ち、成長を遂げる以外にはない、と私は思います。
|
いまでは、私は吉本隆明とその考え方が随分違ってきたのですが、この「対幻想」という考え方の出発点は、よく似ていると思います。
|
|
| (六)「対応」する関係 |
|
人問の「男」と「女」というものの、ペアの「対幻想」というものは非常に大切なもので、これあってこその人間だと思います。
|
私に三十六年間連れ添ってきてくれた妻……。いま初めて私のこのような話を、このような形で聞く妻がこの部屋の隅にいます。少し気恥ずかしい気がいたします。
|
余談ですが、実はちょうど昨日、昭和四十年卒業の三年三組の人たちのクラスー私が初めてこの烏取西高で担任となった時のクラスは三十四年前の一年八組です。その一年八組の生徒達の一部もいた三年生の時のクラスーの人達がクラス会を開き、その折り「洋三の還暦を祝う会」という形で、赤いチャンチャンコを用意して、私の還暦を祝ってくださいました。赤いチャンチャンコを看て記念撮影をした後、謝辞を述べることになったのですが、その席でツイツイ泣いてしまいました。今日お話しながら余り泣かないで済むのは、昨日ある程度涙を流したからだと思います。
|
さて、私の還暦を祝ってくれた、この学年の生徒は私と複雑な結びつきを持っていますが、私にとっては、「他人ごとでない関係」です。いわゆる「相対的な関係」である友達関係ではなく、「絶対的な関係」です。男同士であるにもかかわらず、お尻をさわられて気持ちの良さを感じるような関係とでもいうのですか、「対幻想」に近い関係のような気がします。
|
この学年は、私にとって非常に忘れがたい学年でした。それに比べると、その他の学年の方々は、「担任と生徒の関係」、「学力を基準に受験指導をする先生とその生徒の関係」、「悩みを持つ生徒に対して適切な本を薦める先生という関係」、つまり「対」という関係ではなく「対応」するということを前提とする関係、いわゆる吉本隆明のいう「共同幻想」の関係であったように思います。
|
さて、先に触れましたが、「人問は簡単に信用してはいけない」という意味で、極めて悲しい存在です。しかし、そうではあっても生きていく以上、誰かを信じていく以外にありません。そこでとりわけ人生において生きていく上で重要となるのは、素晴らしい異性との出会いです。私にとって、異性との出会いは非常に重要でしたが、これは高校生の時に気づくべき重要な問題であり、是非伝えておきたいことです。
|
|
| (七)立身出世のワナ |
|
そして、いま一つ伝えておきたいことがあります。それは、私たちより一つ上の世代の人々、いわゆる戦前戦中派の人々の未だ持つ夢についてです。この世代の夢の特徴は何かというと「末は博士か大臣か」というものだと思います。つまり高い高等教育を受けるということは、大臣になったり、博士になったりして、故郷に錦を飾って「立身出世」すること、このことが高等教育の価値あるものだと考えてきたのです。
|
これら戦前戦中派の民衆が看板として掲げてきた「立身出世」いうものは何であったのか。それは「国家主義」という大きな看板を掲げ、強力な国家というもの作ろうとしてきた権力が民衆に対して、準備してい一」うとする「国家主義」というものを、民衆側で気持ちよくソフトに受け入れて、準備してくれるようにし向けた考え方だったのです。つまり立身出世主義は、民衆の側であたかも民衆自身の思想であるかのように考え、民衆自身が夢を描けば、どのようにでも可能になるという形で、権力が用意し、仕組んだ罠であった、と私は患います。
|
この立身出世主義という罠の考え方にはまると、どこかで権力というものが本質的に持つ怖さを見失わせることになります。立身出世主義というものの考え方の中で、人は他人を肘で押しのけて、競争に勝ち抜いていくことこそが、唯一の喜びであるように考えはじめます。
|
こういう権力主義というものとタイアップした立身出世主義というものが、どんなに恐ろしいものを現実の世の中で用意してくるか、それを民衆自身が見極め、気づかなければならない、ということを「私にとっての戦後」という一文で言いたかったのです。しかし、民衆自身が、そのことに対してきちんと整理していないのが実情です。その証拠として、第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争という戦争で、民衆は国民として、国家の一握りの権力者達である軍閥、財閥、官僚閥の思うままに動かされて戦争に駆り出されていったのであって、多くの国民は被害者である、と民衆自身は考えています。つまり国民の大部分が被害者意識をもって戦争を語り、これと逆に、日本国民の大多数こそが、「立身出世主義」を支持する形で戦争に荷担した加害者である、という加害者意識を持って戦争を語るということがあまり見受けられません。
|
国民の多くは、立身出世主義にいう「末は博士か大臣か」という、そんな夢を見続けて、国家権力が操りやすいような人間を作り出してきました。さらには博士となり、大臣となり国家の権力中枢に位置し、そこで権力構造を再生産していく過程に協力し、多くの者がそれを支持するからくりをつくり、「国家主義」と「立身出世主義」にドップリと身をつける者を輩出する教育にだけ目を向けてきたのです。そのあげく、多くの国民は戦争中に両手を上げて、天皇の民、天皇の子として、国家のため、天皇のために死んでいくということを受け入れるような、公民として育てられていったのです。
|
私自身も危ういところで、そのボーダーを踏み越すようなところへ、追いやられていました。ただ、私は幸運なことに、その時小学校三年生であり、国家権力の用意する立身出世主義に組み込まれるには幼なすぎました。従ってこの時期に敗戦という本当の大きな事実に出会い、大人のからくり1立身出世主義1に気がつくことができたことは、私にとっては、ありがたい時期の終戦であったと思います。
|
|
(八)学生・家住・林住・遊行
|
|
次に話をまとめていく上で、ちょうど都合のよいものとして平成四年七月の、私の同窓会ー私は鳥取西高の第六回の卒業生で、昭和三十年卒業ですがーの記念誌の序文を用意しました。本日のこの集まりには昭和四十年卒業の方々が多く、私とちょうど十歳違いますから、昭和四十年卒業の方々は第十六回の卒業生ということになります。
|
私の同窓会では卒業三十五周年の記念として、小さなアルバムを作りました。そのアルバムの記念誌刊行委員として、私自身に刊行の言葉を述べる責任が回ってきました。何を序文に書けぱよいのか少し迷いましたが、この年の正月に読んでいた河合隼雄の著作から思いついたインドの思想について書きました。
|
インドのライフサイクルの考え方は、人生を四期に分けます。人生を六十年生きるとすると各期十五年に分けるのです。このように人生をとらえたインド人も偉いと思いますが、中国人の、還暦という十二年×五1-六十年というサイクルで一生涯を捉える考え方も偉いと思います。
|
さて、このインドのライフサイクルの四つの時期とは、「学生(がくしょう)期」、「家住(かじゅう)期」、「林住(りんじゅう)期」、「遊行(ゆぎょう)期」というものです。
|
学生期というのは、勉強する時期です。確かに、訳の分からない小さな子供が大人になっていくためには、知識というものがどうしても必要です。ただここでいう知識というものは、情報、知恵、というものとの違いをあきらかにしておかなければいけない。情報は一方的にながれるデータであり、知識は情報を自分ものとして吸収するもの、さらに知恵というものはこれを体得する、実践するということが必要になるものです。これらを全て含めたものとしての知識、これを吸収すべき時期をインドでは学生期として、人生の初期に置いています。その学生期を終えると、次は家住期、家を中心にして人問が生活していく時期となります。
|
私がここで重要だと思うことは二つあります。これはあくまで私が重要だと思うことですが、学生期においては「対幻想」の重要性を知る、つまり男と女との出会いに目覚めることの重要性に気づく、そしてここから家というものをつくります。そしてこの家住期においては、子づくり、家づくり、子育てというものが重要になります。家住期では、夫婦は学生期にある子を扶助し、知識を与えていく時期です。ただ、この男女の「対幻想」を少しずつ少しずつ実現するためには、人間は社会という複雑なものの中から生活の糧、収入、所得を得ていくことが必要になります。最近の若い人の考え方では、学生期からいきなり仕事というように「家」はあまり重要でなくなっています。子づくり、子育てなんかどうでもいい、というようになっている。要するに、仕事=金儲けが大切なことになっています。
|
このような若い人たちと違い、先に申しましたが、吉本隆明も人生において「対幻想」を重要視するのですが、これは私の人生に対する思想的姿勢とよく似ていると思います。私は男と女の一対幻想一こそが人生を踏み出す際の大切な第一歩と看えています。従って学生期は家住期を実現させるための時期ととらえていますから、家庭と仕事というものをできるだけ摩擦のないように、出来るだけ両立させていくという方針でいました。インドのこの思想を理解する際にもこのような考え方を基本にしていました。っまり仕事と家庭を両立させることが重要なのです。
|
ところが、学生期にあつた子供達が成長して家住期にはいる時期にさしかかると、親はいよいよ子育ても終わり、さてこれからどうするか、どのように生きていくのかということが問題になります。
|
このときインドの考え方では、親は家住期から林住期に入るということになる。ここがインドのものの考え方の面白いところですが…。林住期は社会というものから一歩離れているのです。今日のこの部屋にも、お坊さんもいらしやるので、少々話にくいところもありますが、私はお寺というものがもっている重要な点は杜会から切り離された点にあると思っています。
|
私は人生においては、家住期というものを大切に考えています。従って仕事というものをそれほど人生では重要視していません。しかし、私より一世代前の方々、あるいは私より若いにもかかわらず保守的なものの考え方をしている人は仕事というものを人生において重要視しています。社会で名をあげたいと思っている、いわば立身出世主義に侵されているこのような人たちは、国家主義にストレートにからめ取られた危険性を持っているのではないでしょうか。
|
しかし、人生とはそ九なものではないはずです。社会から自分を切り離して自分を見つめ直す視点が必要です。つまり個人として生きる、個人をどのように取り戻し、回復するかということが重要になるのですが、これを教えてくれるのが、寺である、と私は思います。この寺というものは、その昔、林の中にあつたわけで、僧が住む場所H林に住む、という形すなわち社会から遮断した形で存在している。しかし僧が住む場所は完全に社会と遮断されているわけではなく、時に社会との接触を持ち、社会に対してシヨックを与え、刺激するということをします。そして社会の矛盾を指摘して、その役目が終わるとまた隔絶した林の中に引きこもります。寺1-僧は杜会との隔絶、接触というこのサイクルを繰り返します。
|
余談ですが、この社会との接触のタイミングが重要です。これを問違えて、社会との接触を取ると、却って社会から非難されるものとなります。たとえば、オウム真理教の問題について、触れる時期ではないにもかかわらず、そのことについて触れてバカにされる僧職の人たちがいます。さて、社会から退いて、林の中に行くと、さらに仏教はここから悟りを得て、遊行期に入るとしています。
|
「人間は何をするためにこの世に生まれてきたのであろうか、所詮遊びではないか、遊びこそ人生である」と悟りの境地に達するのです。このように人生を遊びであると唱えてきた日本人は非常に多い。よくよく考えてみると日本の文化論、宗教論の中心にあるものの考え方は、「遊び」というものです。この「遊び」をどのように、哲学にまで高めていくか、これこそがまた「遊び」であり妙味あるところです。また人生を分かろうとして哲学という堅苦しい学問の書物を読んだりしますが、所詮は肩の力を抜いて、楽な気持ちになって「遊ぶ」ことこそが重要なのだと知ります。人生とは遊びである。このように悟つて、スーと消えるがごとく人生を終えていく、これが遊行期です。
|
|
(九)臨終期
|
|
ちょうど今、私自身は子育ても終わり、その育って行った子供達がいま家住期にさしかかろうとしています。このような時期の昨年八月に癌の告知を受けました。私にとって恩人であり、友人であり、大変な先生でもあります今日ここにおられる片山正見先生から一患者としての浜崎先生は、癌であるとはつきり告知をした上で対応した方が良い患者であると思いますから、全てを告知した上で日赤病院は対応したいと思います。日赤病院の技術が足りないと思えば、浜崎先生ご自身の人脈の広さで癌センター、あるいは先生ご自身の母校の京都大学医学部でも手術が受けられるようにしていただいても結構です。それがお望みならば日赤はそのように対応するつもりです、と言われました。
|
しかし、私自身は「どこで生きてきたのか」と言えば、私は「私と鳥取西高」、「私と日赤病院」、「私と片山正見先生」、「私と徳永進先生」、そういう人と人との関係の中で生きてきました。いまさら自分の病気を見てもらう際に、いかに技術的に優れていようと、自分と何の関わりもない医者、それこそ国家権力に身を阿(おもね)るような形で「末は博士か大臣か」という立身出世主義の中で名医なられた人、そういう医者に私自身の身を委ねる気にはなりません。
|
それよりも、私自身が生きざまとしてきたこと、すなわち人と人との関係を重要視する中に最後まで自分の身を委ねた方がいいと決断しました。癌告知の後も、私という患者の「あそこが痛い、ここが痛い」という訴えを、細かに聞いて対応してくれる日赤病院にご面倒をおかけしたいと決断をしました。
|
その決断の時に「日本という国の時の流れは余りにスピードが速く、インドのような学生期、家住期、林住期、遊行期というゆったりとした時の流れのライフサイクルではない。学生期、家住期、そして猛烈なスピードで『臨終期』に向かいつつあるのではないか」と感じました。徳永先生は「病気は気力が半分である」といわれます。私も、この気力をもって病気に立ち向かえることができるならば、自分の病気を乗り越えることができるかもしれないと思います。あるいは気力をもって病気に立ち向かったとしても、残された時間は絶対的時問からいえば同じかもしれません。
|
しかし、私は残された時間を、電話の受話器もとらず、人にも会わず、何もしないで、生きてゆくのではなく、私の体力の許す限り外を歩き、本も読み、電話の受話器も取ったり、私を訪ねてきてくださる方と少しでも話をする、というふうに、さきのインドの考え方にあった林に住む、「林住期」の実りを持つようにしたいと思います。
|
徳永先生のはからいで、ここでこういうお話をさせていただく羽目になったのですが、それは、「生きようとする意欲をもて」との徳永先生の励ましであると思っています。そして、みなさんの前で講演をさせていただいた今日を、そのように生きる「きっかけ」として与えていただいたように、思います。大変良い機会をあたえていただいたと感謝しております。始まる前は「三十分話すことができればいいな」と思っていましたが、話し始めるとまだまだ一時問くらいは、お話できるような気力があるような気がします。
|
どうも有り難うございました。
|
|
|
|
|
完
|
|
| メールでご注文できます。 teiyu★nifty.com |
| ★をアットマークに変えてお送りください |
|
|
|
|