
|
■ 今月読んだ本
|
第五回
飽食の時代に…
|

|
「人間は平等である」というテーゼは正しい。しかし、所得、自由、効用…のどれを平等化すればよいのか。98年にノーベル経済学賞を受賞したセン(34年インド・ベンガル地方生れ)は、『不平等の再検討』(1992、岩波書店、1999)において、「よりよい生活」とは、適切な栄養状態や健康状態、社会生活への参加や自尊心の維持など多岐にわたる「機能」の集合、すなわち「潜在能力」によって決められ、「潜在能力」の平等こそが「生き方の幅(自由)」を拡大する、と主張した。
|
「ベンガル(1942〜44)、エチオピア(72〜74)、サヘル地域(68〜73)、バングラデシュ(74)の飢饉を分析した『貧困と飢饉』(1980、岩波書店、2000)でセンは、飢饉は例年に比べて食糧供給が増加しているときでも起こっている、と常識を覆す。飢饉とは、ある集団が十分な食糧を手に入れ消費する能力や資格(エンタイトルメント)を失った結果である。
|
戦後生まれが多数を占める日本では、飢饉という語にリアリティーを感じることは難しい。しかし、空前の好況を享受するアメリカですら、インドの寒村より所得がはるかに高いのにもかかわらず貧困にあえぎ毎日の食事に事欠く人々が少なくない。
|
死者300万人とも言われるベンガル大飢饉を経験したことがセンを経済学に向かわせた。冷静な分析の裏に、不平等・貧困・飢饉の根絶を希求する彼の熱き思いがにじみ出る経済学=倫理学的探究の基本書である。
|

|
|

|
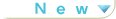
|
○柳父章
|
○椎名健
|
○澤井啓一
|
○小谷敏
|
○岩田直樹
|
○澤弘一
|

|

|

|
岩田 直樹
(いわた なおき)
|
|
高校で数学を教える。十代後半から二十歳過ぎまでは人並みに小説を乱読したが、ここ十年ほどは、現象学からはじめて、思想書をゆっくりと読み進んでいる。
|

|

|
告知板
|
|
|
|