
|
|
■ 今月読んだ本
|
|
| 第237回 宇沢弘文の社会思想から「あいだ」の哲学へ(7) |
|

|
|
3.宇沢弘文の社会思想-社会的共通資本を中心に
(4)社会的共通資本とは何か
イ)地球環境
自然環境(土地、大気、土壌、森林、河川、海洋など)、社会的インフラストラクチャー(道路、上下水道、公共交通機関、電力、通信施設など)、制度資本(教育、医療、金融、司法、行政など)に大別される社会的共通資本の中でも、生物としての人間の生存の直接的基盤となるのは自然環境、とりわけ大気である。『自動車の社会的費用』(1974年)の刊行、水俣病をはじめとする公害問題への関与などによって社会的共通資本論を深化させていった宇沢は、地球環境(地球温暖化)問題に関する論考を世に問うていく。
1950年代から1960年代にかけて極端な形で発生した公害問題、環境破壊が初めて国際的な議題になったのは、1972年にストックホルムで開催された「国連人間環境会議」である。先進国と途上国の双方に配慮して、前者における環境保護の優先、後者における開発優先と援助増強を盛り込んだ「人間環境宣言」が採択された。産業活動によって硫黄酸化物、二酸化窒素、有機水銀など有毒物質が排出され、自然環境は破壊・汚染され、さらには人間の生命・健康が脅かされていた。ストックホルム環境会議のアジェンダを象徴していたのは日本から参加した水俣病患者であった。
1980年代はオゾン層破壊問題がクローズアップされる。1985年に採択された「オゾン層保護のためのウイーン条約」に基づき、1987年にオゾン層を破壊する物質(特定フロン、ハロン、四塩化炭素など)の製造・消費・貿易を規制する「モントリオール議定書」が採択された。また、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は1988年に設立されている。
1992年にリオ・デ・ジャネイロで開催された「地球サミット(環境と開発に関する国連会議)」の主要なテーマは20年前のストックホルム環境会議のそれとは本質的に性格の異なるものであり、理論的にも政策的にもはるかに困難な問題を提起した。二酸化炭素などそれ自体は無害な化学物質が産業活動、都市活動などによって大量に排出され、地球的規模における自然環境の均衡を攪乱して不可逆的な影響を及ぼす。地球温暖化、生物多様性の喪失、海洋汚染、砂漠化の進行などは「豊かな国々」(近年の用語を使うとグローバル・ノース)の経済活動によって惹き起こされ、直接的な被害を受けるのは「貧しい国々」(グローバル・サウス)である。南北問題は解決されるどころか格差がますます拡大している。
地球サミットの成果は次の5つの宣言・条約である。「環境と開発に関するリオ・デ・ジャネイロ宣言」(持続可能な開発に向けた地球規模での新たなパートナーシップの構築)、「アジェンダ21」(21世紀に向け持続可能な開発を実現するために各国および関係国際機関が実行すべき行動計画)、「森林原則声明」(すべての種類の森林経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明)、「気候変動枠組条約」(大気中の温室効果ガス濃度の安定化によって気候変動がもたらす悪影響の防止のための取組原則)、「生物多様性条約」(生物多様性の保全・持続可能な利用、遺伝資源から生じる利益の公平かつ衡平な配分)であり、21世紀の地球環境問題対策の枠組みがほぼ出揃っている。
佐々木実はインタビューした際、宇沢が問わず語りに「沈黙の10年間」を話した様子をこう記している。「日本に帰ってきてから、とくに水俣とか環境破壊の現場を何年間も歩いていた。経済学の限界を感じて、ものすごく経済学に頭にきているときでね。それでかなり突き詰めて、新古典派経済学とは何かと。ぼくはそれまで、ほとんどの経済学の論文は読んでいたし、個人的にもサミュエルソンやフリードマンらともさかんに議論をしていた。そうしたものをもとに、ぼくなりに新古典派経済学の原型を考え、それを批判した。……一時完全に経済学と別れた時期が、10年ぐらいあるんですよね。……全国をまわり歩いて。ぼく自身、それまで求めてやってきたことと現実とのギャップがあまりにも大きかった。現実の問題をどうやってぼく自身がとらえるのか。そういう結構苦しい時代だったんですよ。だけど、やっぱり経済学を志した以上、なんとか経済学の考え方に(自分の問題意識を投影していきたいと)」(前掲『資本主義と闘った男』445頁)。
宇沢は1989年3月に東京大学経済学部を定年退官する。その前年に2冊の論文集を刊行している。『Preference,Production,and Capital:Selected Papers』(ケンブリッジ大学出版会、『選好、生産、資本』、タイトル訳は岩田、以下同様)、『Optimality,Equilibrium,and Growth:Selected Papers』(東京大学出版会、『最適性、均衡、成長』)であり、前者には19本の論文が収められている。発表は1960年代が13本、1950年代と1970年代が3本ずつ。1980年代の論文は1本もない。1974年の論文が最も新しい。とすれば、宇沢が世界に発信した研究には本人が語るように確かに10年以上の「空白」がある。
佐々木は「沈黙」と表現するが、この間、宇沢は「沈黙」していたわけではない。1995年までに執筆された著作や論文を収録した『著作集』で明らかなように精力的に言論活動を行っていた。社会的共通資本の論理と具体的内容をより精緻に練り上げていった時期であった。自らの思想を宇沢本人が開拓しつつあった新たな経済学の枠組みに落とし込もうと模索していたのである。
1990年代に入ると宇沢は立て続けに英語、日本語の論文や著作を次々と発表していく(英語論文の掲載誌は『宇沢弘文の経済学―社会的共通資本の論理―』日本経済新聞社、2015年、219頁、参照)。
代表的な英語論文は「Global Warming Initiatives:The Pacific Rim」(1991年、「環太平洋地域における地球温暖化イニシアティヴ」)、「Imputed
Prices of Greenhouse Gases and Land Forests」(1991年、「温室効果ガスと森林の帰属価格」)、「The
Tragedy of Commons and The Theory of Social Overhead Capital」(1992年、「コモンズの悲劇と社会的共通資本の理論」)、「Equity
and Evaluations of Environmental Degradations」(1993年、「公正性と環境劣化の評価」)、「Global
Warming and the International Fund of Atmospheric Stabilization」(1995年、「地球温暖化と大気安定化国際基金」)。国内向けには「地球温暖化の経済学」(雑誌『世界』岩波書店、1991年3月号)、『地球温暖化の経済分析』(國則守夫との共編、東京大学出版会、1993年)、『地球温暖化の経済学』(岩波書店、1995年、『著作集Ⅺ 地球温暖化の経済分析』所収)、『地球温暖化を考える』(岩波新書、1995年)がある。(これらの集大成が地球温暖化問題と社会的共通資本を論じた『経済解析 展開編』岩波書店、2003年と『Economic
Theory and Global Warming』ケンブリッジ大学出版会、2003年、『経済理論と地球温暖化』である。)
宇沢が地球温暖化問題に力を尽くしたのは必然だった。社会的共通資本としての地球環境を未来世代のために保全することは、「それまで求めてやってきたこと」=「従来の経済学の枠組みの精緻化」と「現実」=「これまでの経済学では切り捨てられてきた問題」のギャップを埋める理論的実践的営為にほかならなかったからである。
1990年にローマで開かれた地球温暖化に関するシンポジウムで、宇沢は一人当たりの国民所得を考慮する「比例的炭素税」、いわゆる「宇沢フォーミュラ」と「大気安定化国際基金」を提唱した(後述)。大多数の経済学者の賛同は得られたが、アメリカの研究者は厳しく批判した。アメリカ政府が地球温暖化対策にきわめて消極的なのは周知の事実であった。(前掲『メッセージ』167―168頁、参照)
また、1995年に箱根で開催された「環境と持続可能な経済発展」に関する国際シンポジウムにおいて、公正・正義の概念に基づく比例的炭素税、大気安定化国際基金の構想をさらに発展させて、「自然環境などの社会的共通資本の賦与量が国によって異なるとき、自由貿易主義の根幹をなす比較優位の原則に対して、どのような形で修正を加えなければならないかについて、重要な理論的貢献がおこなわれた。」(前掲『宇沢弘文の経済学』217―218頁)箱根シンポジウムには、ケネス・アロー、デール・ジョルゲルソン(1933―2022)、ウィリアム・ノードハウス(1941―、2018年に「気候変動を長期的マクロ経済分析に統合した功績」でノーベル経済学賞受賞)ら世界最高峰の経済学者が参加していた。
宇沢はノードハウスについて「非常に悪い役割を果たしています」と後に語っている(前掲『宇沢弘文傑作論文ファイル』217頁)。ノードハウスは、宇沢がシカゴ大学で開催したワークショップに参加していた教え子であり、1977年から1979年にかけてカーター政権下で大統領経済諮問委員会の委員を務めた。1970年代、真鍋淑郎(1931―、2021年ノーベル物理学賞受賞)が提唱した「大気海洋結合モデル」によって二酸化炭素濃度が2倍になると平均気温が2度以上も上昇する地球温暖化の詳細なメカニズムが解明されつつあった。地球温暖化が初めてホワイトハウスで取り上げられたとき、この問題を担当したのがノードハウスである。
地球温暖化問題は科学的に証明できないという立場を取っていたノードハウスは、1991年段階で「温暖化は起こっているかもしれない。起こるかもしれない。しかし、それは何の影響もない。ノン・プロブレムだ」と語っていた。その後、「わずかな費用をかければ温暖化の被害は十分に防げる」と地球温暖化対策に言及するようになり、海水面の上昇に対しては「防波堤を作れば簡単に防げる」、農業に対しては「農民は今までも苦労してせっせとやってきた。だから、これからも苦労してこの問題をうまく解決するだろう」と発言し、多くの人たちの憤激を買っている(同218―219頁)。
1997年に開催された第3回気候変動枠組締約国会議(地球温暖化防止京都会議、COP3)において、先進国限定とはいえ初めて温室効果ガス排出削減目標を課す京都議定書が採択された(アメリカ議会は批准拒否)。排出量削減を促す「京都メカニズム」の一つに採用されたのは炭素税ではなくノードハウスらアメリカの経済学者が提案した「排出権取引Emission
Trading」であった。排出枠を超えた国が排出量を限度内に抑制した国や事業の「炭素クレジット」を買い取ることによって排出目標達成と見做されるシステムである。宇沢は従来の経済学が考察の対象としてこなかった自然環境を市場取引の対象にする排出権取引を厳しく批判し、排出量は逆に増大すると指摘した(同219―220頁、「地球温暖化と倫理」2002年、佐々木毅・金泰昌編『公共哲学第9巻 地球環境と公共性』東京大学出版会、2002年、所収、40―42頁、など)。その後、温室効果ガス排出量は一向に減少せず、地球の気温が上昇し続けていることは誰しも知っている事実である。2023年7月にグテーレス国連事務総長が「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化(global
boiling)の時代が来た」と警鐘を鳴らしたように、私たちは「気候変動地獄へと向かう高速道路を、アクセルを踏んだまま走っている」(2022年COP27でのグテーレスの発言)のである。
なお、炭素税については1990年にフィンランド、1991年にスウェーデンとノルウェー、1992年にデンマークが導入するなど主にヨーロッパで炭素税導入の動きがある。しかし、グローバル・ノースとグローバル・サウスの対立など国際政治が絡むため世界的な潮流とはなっていない。日本でも環境省が中心となり炭素税導入を検討したが、経団連、日本商工会議所など経済団体の強硬な反対によって2012年に1世帯1ヶ月当たり約100円を負担する地球温暖化対策税が導入された。
ところで、比例的炭素税、大気安定化国際基金はどのようなものか。主に『地球温暖化の経済学』と『地球温暖化を考える』によって概略を説明しよう。
1995年に岩波書店から刊行された両著は想定する読者層が異なっている。宇沢は『地球温暖化を考える』で2つの本の関係をこう書いている。「私はさきごろ、岩波書店から『地球温暖化の経済学』という書物を出していただきました。この書物は、経済学、地球科学など専門の研究者を念頭において書いたものでした。岩波書店の大塚信一さんから、この書物の内容を一般読者にわかりやすいかたちで書いたらという示唆をうけました。私は前々から、地球温暖化の問題について、中学校、高等学校の皆さんにわかってもらえたらという夢をもっていました。」(「はしがき」ⅲ)『地球温暖化を考える』には数式が全く出てこない。
『地球温暖化の経済学』の各章のタイトルを列挙してみよう。プロローグ「「病んでいる」地球」、第1章「地球温暖化―その地球科学的考察」、第2章「地球温暖化と気候変動」、第3章「環境難民の問題」、第4章「工業化・都市化と地球温暖化」、第5章「森林と地球温暖化」、第6章「社会的共通資本の理論」、第7章「温室効果ガスと森林の帰属価格」、第8章「炭素税と経済成長」、第9章「各国の温暖化対策」、第10章「大気安定化国際基金の構想」。一方、『地球温暖化を考える』は序章「地球温暖化の脅威」、第1章「地球の環境を守る仕組み」、第2章「地球の歴史と平均気温」、第3章「地球温暖化の影響」、第4章「矛盾にみちた現代文明」、第5章「熱帯雨林の役割」、第6章「炭素税の考え方」、第7章「二十世紀文明に対する反省」、第八章「新しい展望を求めて」である。『地球温暖化を考える』第8・9章でレールム・ノヴァリム、成田問題などに言及される以外は、専門家向けと一般読者向けの書き方(文体の硬軟など)に違いがあるとはいえ2著作ともほぼ同じ内容である。
両著を一読した感想は「驚き」である。前半部分では地球科学者でも手際よくまとめることの難しい複雑な地球環境問題がわかりやすく論じられている。後半部分では新しい経済学の枠組みが提唱されている。地球温暖化に関して地球科学、経済学のいずれかの側面を上手く論じる研究者は存在するだろう。その両方ともなると至難の業である。しかも、専門家向けと一般読者向けにほぼ同じ内容の質の高い解説を可能にする研究者はそうはいない。2著作を読むだけでも宇沢が超一流の研究者であることがわかる。「地球科学×経済学」の名著であり、刊行から約30年経っても全く色褪せていない。
ここでは地球温暖化のメカニズムやその影響には触れることなく、比例的炭素税の導出方法と内容、大気安定化国際基金の概要について論及する。
社会的共通資本の重要な構成要素である大気の価値は「帰属価格Imputed Prices」の概念によって測定することができる。帰属価格は「生産要素ないし生産物の価値を、最終的な消費のプロセスを通じて生みだされる効用の大きさに帰属して求めようとしたもの」(『著作集Ⅺ』10頁)であり、「陰の価格Shadow Prices」とも呼ばれる。
現在世代が化石燃料を大量消費して大気中の二酸化炭素濃度を上昇させるとき、社会的共通資本としての大気の価値はどれくらい低下するのか。まだ生まれていない将来世代が受ける被害を帰属価格(シャドウ・プライス)として可視化することによって現在世代の市場価格体系に組み入れようとするアクロバティックな理論が求められる。宇沢は自らが構築した最適経済成長理論(「宇沢の定理」1961年、「Neutral Inventions and the Stability of Growth Equilibrium」、The Review of Economic Studies 28(2)、「中立的な発明と成長均衡の安定性」)を帰属価格に適用して現在世代と将来世代の不均衡問題を考察していく。
「現在時点において大気中の二酸化炭素の蓄積量が限界的に1トン増えたときに、将来の世代にどれほどの被害を与えるかということを推計して、適当な割引率によって、その割引現在価値をとったのが、二酸化炭素1トン当たりの帰属価格である。」(『著作集Ⅺ』11頁)
しかし、帰属価格に基づいて炭素税を課税するだけであれば国家間の資源・所得配分の公平性は確保されない。地球温暖化が先進国の経済活動に起因するのは明らかである。各国一律の炭素税を課すことは経済正義の観点から容認できない。途上国の負担を増やして経済発展を妨げることになるばかりか、全世界が一丸となって取り組まなければならない二酸化炭素排出削減に賛同しない国がさらに増えてしまうだろう。
宇沢の卓見は各国間の経済格差を是正するための理論枠組みを創出した点にあった。いわゆる「宇沢フォーミュラ」である。数式は省略するとして(詳しい数式については『地球温暖化の経済学』第6章以降を参照、簡略化したものは『旅』251―256頁)、基本的な考え方は次のとおりである。
基準年度(1990年)の一人当たり実質国民所得水準が二酸化炭素の帰属価格に比例するという前提に立つ。このとき、比例定数(帰属係数)、社会的割引率(通常は5%程度)、海水面によって吸収される大気中の二酸化炭素の割合(通常2-4%)、人々が地球温暖化の影響をどの程度深刻に受け止めているかを表わす指標(0から1の間)、世界人口、クリティカルな二酸化炭素の蓄積量、現時点における二酸化炭素の蓄積量の関係が2つの数式で表される。
二酸化炭素以外のメタン、フロンなどについても同様に算出できる。その結果、18ヶ国の炭素税(温室効果ガス1トン当たりの帰属価格)が導出された。日本が「ジャパン・アズ・ナンバー1」と言われていたバブル経済末期の数字が使われているため、日本の炭素税が最も高くなっている。日本・スウェーデン190ドル、デンマーク180ドル、アメリカ170ドル、カナダ・フランス160ドル、ドイツ・イタリア・オランダ150ドル、イギリス130ドル、オーストラリア120ドル、ニュージーランド90ドル、シンガポール84ドル、韓国35ドル、マレーシア18ドル、タイ9ドル、フィリピン5ドル、インドネシア4ドル。(『著作集Ⅺ』188―189頁の表7-1、『地球温暖化を考える』154―155頁の表5、出典はWorld
Resources,1992-93,Table24.1,and Table24.2(1991,1993))
宇沢が提唱したもう一つの制度的枠組みが比例的炭素税を前提とした大気安定化国際基金である。「大気安定化国際基金は、各国が徴収した炭素税収(森林補助金を差し引いて)の一部を供託することによって、その基金がつくられる。たとえば、年々、各国の炭素税の純税収の10%を、この基金に供託する。大気安定化国際基金は、これらの供託金をプールして、ある一定のルールにしたがって、発展途上諸国に配分する。たとえば、1人当たりの国民所得と人口に依存して、比例配分的なルールで配分するわけであるが、発展途上諸国は、それぞれ受け取った額を、大気均衡の安定化と経済の調和的発展のために支出する。大気均衡の安定化と経済の調和的発展が具体的にどのようなことを意味するかについての定義と支出にかんする要件とを明確に規定して、事前に諒解を得ることが必要となることはいうまでもない。」(『著作集Ⅺ』252頁)
例えば、2023年にアラブ首長国連邦で開催されたCOP28では議論が紛糾して最終的に「化石燃料からの脱却」という玉虫色の成果文書が採択されたことを考えれば、比例的炭素税、大気安定化国際基金は「絵空事」ではないか、との批判は当然である。途上国への援助基金が目的通りに使われない可能性もある。
そもそも社会的共通資本が従来の経済学にとって絵空事であった。宇沢は空論と謗られようとも現実に一歩でも近づき未来世代に少しでも貢献するために地球温暖化問題に取り組んだのである。例えば、いつ到来するかわからない「脱成長コミュニズム」や「交換様式D」を夢想するだけで到達への道筋を示さないような思想家ではなかった。生活者の視点から物事を考える地に足の着いた実践的な研究者であった。
1990年11月、宇沢は成田空港(新東京国際空港)建設の反対同盟のメンバーたちから手紙をもらった。成田闘争の経緯と現状、空港周辺地区の荒廃、社会的関心の風化、闘争の当事者たちの悩みなどを綴り、問題解決に協力してくれないか、という内容だった。宇沢は、地球温暖化の問題への取り組みを通して社会的共通資本の理論を本格的に展開しようと覚悟を決めたところだったので、断りの手紙を書かざるをえなかった。「成田空港問題は私にとってあまりにも深刻であり、あまりにも広範な、そして困難な問題を含んでいて、とても私のような一介の学者にとって、果たすべき役割などありようがないと思われた」からである。(『「成田」とは何かー戦後日本の悲劇ー』岩波新書、1992年、40頁、以下『成田』)。
宇沢は『地球温暖化問題を考える』の最終章「新しい展望を求めて」で成田問題を取り上げた。「コモンズの破壊と再生」の観点から農村を再編成し農社の組織を中心とする農業の持続的可能性を具現化したい、と「地球的課題の実験村」構想を提起したのである。
成田問題とは一体何だったのか。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 宇沢弘文の社会思想から「あいだ」の哲学へ(8)へ |
|
 |
|
|

|
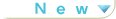
|
|
|
○今月読んだ本
|

|

|
|

|
岩田 直樹
(いわた なおき)
|
|
高校で数学を教えていた。定年退職後の2022年4月から地元大学に勤務。十代後半から二十歳過ぎまでは人並みに小説を乱読したが、それ以降は、現象学からはじめて、思想書をゆっくりと読み進んでいる.。著書に『橋田邦彦・現象学・アーレントの再解釈』(2023年)がある。 |
|
back number
|
 バックナンバーヘ バックナンバーヘ
|
|
|